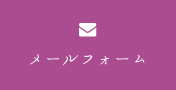令和6年5月23日 大興善寺契園は新緑がきれいです。あじさいも咲いてきてます
2023-05-23
令和6年のつつじ祭りもあっという間に日にちがたち、無事に終了いたしました。
ご来園の皆様、ありがとうございました。
今年も4月20日過ぎから満開を迎え、以前のようにゴールデンウイークの満開になっていたころは、古のことになったようです。
「うつし世の浄土うれしや小松山 花のたよりを偲ぶふるさと」
現在は、サツキの花と、アジサイが咲き始めました。
どうぞ、四季折々の季節を大興善寺でお過ごしください。
お盆の季節になりました
2023-08-07
お盆は、ご先祖の御霊をお迎えして、ご先祖様を供養する行事です。ご先祖様が、お客様としてご家庭の仏壇にかえって来られますので、ご先祖様にお供えをして、読経の供養をいたします。
お盆とは、古いインドの言葉のウランバーナ(逆さに吊るされた苦しみ)を、中国では(うらぼん)といい、うらぼんを略した言葉です。
お釈迦様のお弟子の目連(もくれん)さんが、亡き母がどこに行かれているか神通力で見ましたところ、餓鬼道に落ちて苦しんでおられることがわかりました。それで、お釈迦様に相談したところ、7月15日は、お坊さんたちが夏の修行が終えた日なので、その供養の功徳によって救われたという故事からお盆が始まるようになったといわれてます。
お盆には、ご先祖様があの世から帰って来られますので、大切におもてなしをして、ご先祖様に感謝したいものです。私たちがこの世に生まれたということは、ご先祖様があって初めて生まれることができます。
大興善寺では、お盆のお参り、そして、8月16日には、恒例のお施餓鬼の行事を致しております。ご先祖様と私たちが非常に縁の深いことを感じていただきたいと思います。
(写真は、8月16日 施餓鬼のお参り壇)
令和5年4月13日 大興善寺契園開園しました。
2023-04-14
令和5年4月13日(木)、晴天の中、令和5年つつじ祭り開園式が、松田一也基山町長、佐賀県観光課長をはじめ、多数のご来賓の方がご参集のもと、基山町観光協会田口英信会長の開式の挨拶、大興善寺名誉住職の開園宣言が行われました。
ご来賓の皆様方、ありがとうございました。
大正年間の末から、大興善寺境内の裏、契山のふもとの雑木林につつじの植樹をはじめ、現在の契園(つつじ園)となっております。
おおよそ100年前に始まったつつじの植樹から、地元の皆様をはじめ関係各位のご協力ご支援により、本年もお花が咲いております。
「うつし世の浄土うれしや小松山 花のたよりを偲ぶふるさと」
4月22日(土)には、JR九州ウォーキング「「つつじ寺」大興善寺と歴史の町「基山町」を訪ねて」、
きやま門前市が開催されます。
どうぞ、4月中旬から5月上旬にかけまして、ごゆっくり 大興善寺のつつじのお花見にお越しください。
「観音妙智力」 お観音様の救い
2022-08-24
8月のお盆、お施餓鬼の行事も終わり、令和4年壬寅もあと4か月少しになりました。
新型コロナウイルス感染症の「第7波」拡大、ロシアがウクライナに侵攻して半年になりますが、停戦は遠く、世界中で大変な日々が続いております。健やかで安寧な日常が一日も早く戻ってほしいものです。
私たち個人につきましても、「四苦八苦」といわれていますように、一人一人何らかの苦しみを抱えているのではないでしょうか。
大興善寺は、ご本尊様が十一面観世音菩薩様でいらっしゃるので、朝の勤行に観音経を読誦いたしております。観音経は、法華経の第25番目のお経で、観音様の大いなる救いが説かれています。
・「南無観世音菩薩」一心に唱えれば三毒七難を逃れることができる
三毒(貪欲、瞋恚、愚痴)、七難(火難、水難、風難、刀杖難、鬼難、枷鎖難、怨賊難)
・三十三身に変化して私たちを助けてくれる(いろいろな姿に変化して助けてくれる)
・抜苦与楽(苦を除いて、楽を与えてくれる)
観音様の霊験とご利益は、古から多々語り継がれております。多分、信仰することで、観音様の大いなるお慈悲を感じることができるものだと思います。
昔、後白河法皇が、今様諸歌謡を集成された「梁塵秘抄」に
「観音誓ひし廣ければ、普き門よりいでたまひ、三十三身に現じてぞ、十九の品にぞ法は説く」という歌があります。
私たちが願いを叶えたいと思ったとき、まずは、私たち自身の努力が一番ですが、「一心称名」と申しまして、心からお観音にお願いすることで、古から願いが叶ってきたと信仰されています。(令和4年8月)
新春のご挨拶
2022-01-06
新年あけましておめでとうございます。
令和4年壬寅の歳を迎え、本年が皆様にとって良い年でありますことを、お祈り申し上げます。
令和3年は、新型コロナ感染症の拡大の中、大変な日々であったかと思いますが、本年は、神仏のご加護と、人類の英知により健やかで安寧な日常が戻ってくることを望んでおります。
さて、大興善寺本堂は、令和3年秋より、茅葺き屋根替え(一部(本堂奥))をおこなっております。今回の屋根替えにつきましては、基山町街なみ整備助成事業等補助金の支援を受けており、基山町の支援に大変感謝致しております。
令和4年3月には、本堂の奥は、新しい茅葺き屋根に生まれ変わります。
お寺の風景(街なみ)が、来山される方の心の安らぎになるよう、努めてまいります。